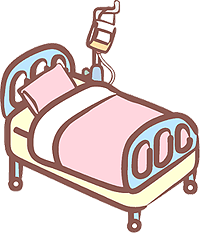

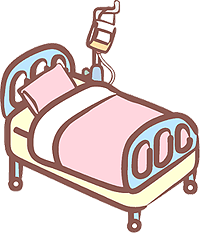
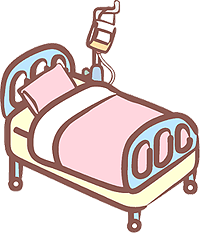

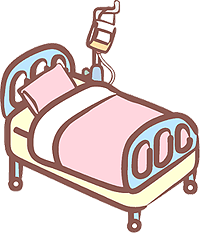
| 限度額認定証を利用した場合、本来の窓口負担額が所得区分に応じた自己負担限度額を 上回った場合でも、支払いは限度額までに抑えることができます。 自己負担限度額・所得区分は高額療養費と同じです。 |
 ■①組合員が窓口で組合員本人分を申請する場合■ ○限度額適用・標準負担額減額認定申請書 ○印鑑 ○「負傷原因報告書」(ケガの場合) ○組合員の保険証 ○組合員のマイナンバー通知カード、 もしくは個人番号カード(顔写真入りのもの) ○組合員の公的な身分証明書【官公署発行の顔写真入りのもの】 *個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要 |
| ■②組合員が窓口で家族分を申請する場合■ ○限度額適用・標準負担額減額認定申請書 ○印鑑 ○「負傷原因報告書」(ケガの場合) ○組合員の保険証 ○組合員のマイナンバー通知カード、 もしくは個人番号カード(顔写真入りのもの) ○家族の個人番号が分かるもの ○組合員の公的な身分証明書【官公署発行の顔写真入りのもの】 *個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要 |
| ■③代理の方が窓口で組合員本人分を申請する場合■ ○限度額適用・標準負担額減額認定申請書 ○印鑑 ○「負傷原因報告書」(ケガの場合) ○組合員の保険証 ○委任状 ○組合員のマイナンバー通知カードのコピー、 もしくは個人番号カードのコピー(顔写真入りのもの) ○代理人の公的な身分証明書【官公署発行の顔写真入りのもの】 |
| ■④代理の方が窓口で家族分を申請する場合■ ○限度額適用・標準負担額減額認定申請書 ○印鑑 ○「負傷原因報告書」(ケガの場合) ○組合員の保険証 ○委任状 ○組合員のマイナンバー通知カードのコピー、 もしくは個人番号カードのコピー(顔写真入りのもの) ○家族の個人番号が分かるもの ○代理人の公的な身分証明書【官公署発行の顔写真入りのもの】 |
|
○所得がわかる書類について○ ●所得情報を得られた場合→自宅に認定証を郵送 |
※中学生以下の方は組合様式の「所得に関する申告書」をご提出ください。 ※委任状はホームページでダウンロードできます。 |
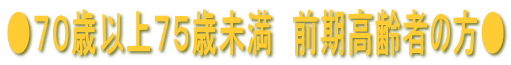
| ●現役並み所得世帯Ⅲ・一般世帯の方は「限度額適用認定証」の申請は必要ありませんので、医療機関等の窓口で保 険証と一緒に「高齢受給者証」を提示してください。 ●現役並み所得世帯Ⅱ・Ⅰ、低所得Ⅱ・低所得Ⅰ世帯の方は、高齢受給者証では限度額認定証としてご利用すること ができません。その場合、限度額認定の申請が必要になってきますので、詳細は支部までお問い合わせください。 【電話:075-211-5844】 |
| ■①組合員が窓口で組合員本人分を申請する場合■ ○限度額適用・標準負担額減額認定申請書 ○印鑑 ○「負傷原因報告書」(ケガの場合) ○組合員の保険証 ○組合員のマイナンバー通知カード、 もしくは個人番号カード(顔写真入りのもの) ○組合員の公的な身分証明書【官公署発行の顔写真入りのもの】 *個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要 |
| ■②組合員が窓口で家族分を申請する場合■ ○限度額適用・標準負担額減額認定申請書 ○印鑑 ○「負傷原因報告書」(ケガの場合) ○組合員の保険証 ○組合員のマイナンバー通知カード、 もしくは個人番号カード(顔写真入りのもの) ○家族の個人番号が分かるもの ○組合員の公的な身分証明書【官公署発行の顔写真入りのもの】 *個人番号カード(顔写真入りのもの)をお持ちいただく場合は不要 |
| ■③代理の方が窓口で組合員本人分を申請する場合■ ○限度額適用・標準負担額減額認定申請書 ○印鑑 ○「負傷原因報告書」(ケガの場合) ○組合員の保険証 ○組合員のマイナンバー通知カードのコピー、 もしくは個人番号カードのコピー(顔写真入りのもの) ○代理人の公的な身分証明書【官公署発行の顔写真入りのもの】 ○委任状 |
| ■④代理の方が窓口で家族分を申請する場合■ ○限度額適用・標準負担額減額認定申請書 ○印鑑 ○「負傷原因報告書」(ケガの場合) ○組合員の保険証 ○組合員のマイナンバー通知カードのコピー、 もしくは個人番号カードのコピー(顔写真入りのもの) ○家族の個人番号が分かるもの ○代理人の公的な身分証明書【官公署発行の顔写真入りのもの】 ○委任状 |
| *自己負担限度額の区分の詳細は、【医療費が高額になったとき】の案内に記載されています。 |